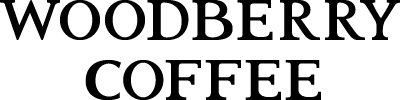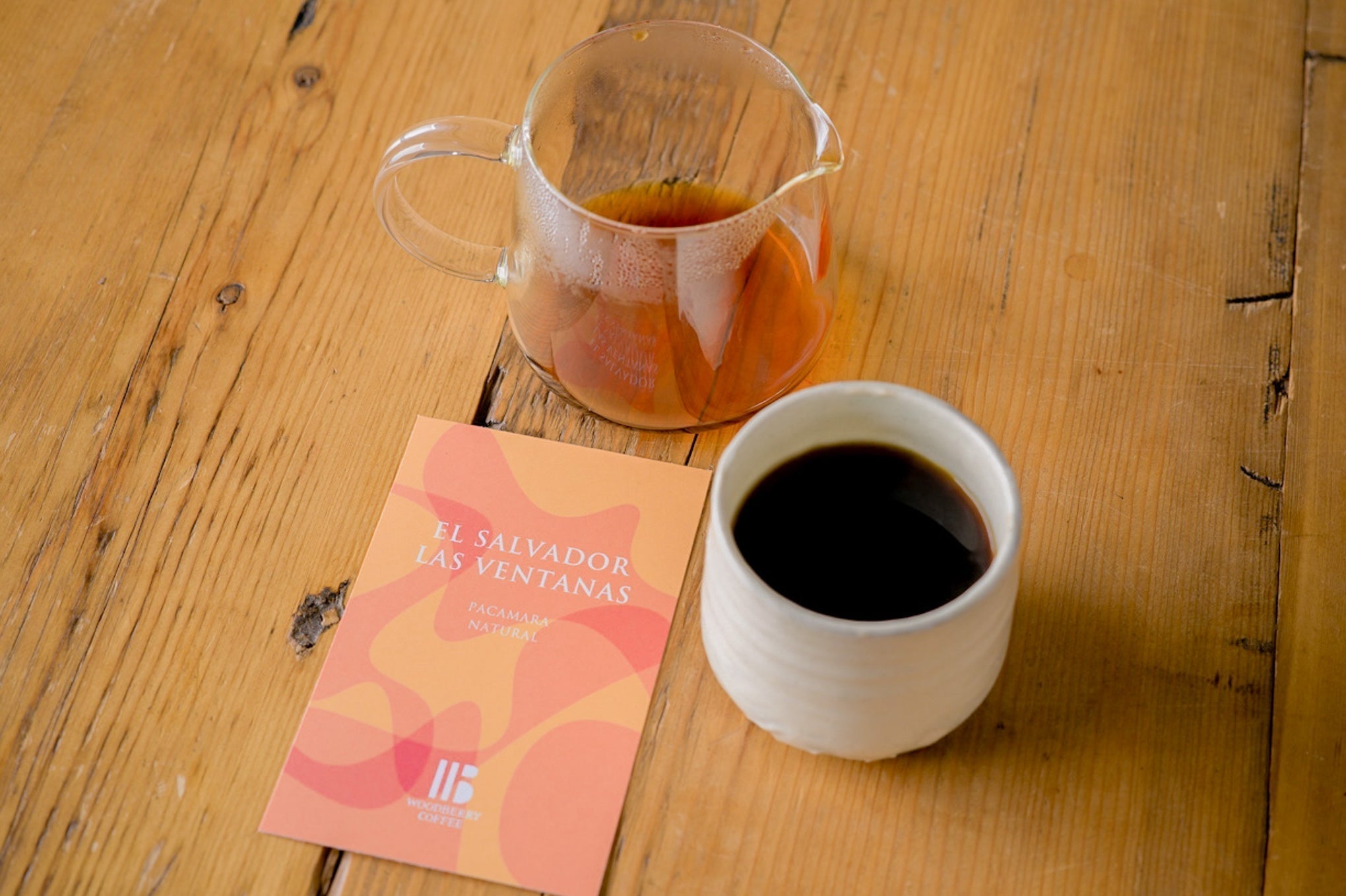Vegans and the Future of Food
Part01 「ヴィーガンだから美味しい」という信念 吉松 努
ウッドベリーでは「身体にも地球にも優しく」をテーマに、お店で提供する料理や焼き菓子・パンに有機野菜や無添加にこだわった食材を使用しています。また、多様な食習慣を考えたヴィーガンやグルテンフリーのメニューを幅ひろく取りそろえています。
なかでも、近年とくにヴィーガンメニューを求めてお越しになるお客様が増えていることを実感します。
ヴィーガン(完全菜食主義者)とは、動物福祉や環境保全の観点から、肉や魚、卵や乳製品、蜂蜜などの動物由来のものを一切食べない人たちのことです。
サステナビリティへの意識の拡大やインバウンド需要の増加によって、日本でもヴィーガン/ヴィーガニズムが注目を集めるようになったいまでこそ、東京にはヴィーガンメニューが食べられるお店がたくさんありますが、私たちが提供をはじめた 2019 ~ 2020 年ごろはそれほど多くありませんでした。当初は一部のメニューとして試験的に導入したヴィーガンメニューでしたが、反響も大きく、気づけばメニューの中心的な存在に変わり、現在は 6 種類のフードと、ベーカリーでつくっているほぼすべてのお菓子・パンがヴィーガンレシピのものになっています(ベーカリーでは、季節ごとに変わるお菓子が約 20 種類、パンは 10 種類以上の取り扱いがあります)。
ヴィーガン料理はまだまだ新しいジャンルの料理といえます。「ヴィーガン」と聞くとどこか我慢を強いられるような印象を抱く方もいらっしゃるかもしれませんが、私はヴィーガン料理も一般的な料理と同じように、あるいはそれ以上に美味しいものをつくることができると考えています。同時に、すべてのお客様がヴィーガンに関心をもっているわけではないので、それを意識せずとも美味しいと思っていただけるようなものをつくりたい。そうした想いから、「ヴィーガンでも美味しい」ではなく「ヴィーガンだから美味しい」ものをつくることを信念としています。
ヴィーガン料理は新しいものだからこそ、可能性に満ちあふれています。そのなかには、味わいとしてだけでなく、人(の食事)が生態系や環境に対して与える影響について見直すための契機もふくまれています。今月からはじまるこの巻頭コラムでは、ヴィーガン料理にフォーカスしながら、食と地球の未来について考えていきたいと思います。

私がみてきた世界の食文化
まずはじめに、簡単に私の経歴をお話しさせてください。
私が料理人を志したのは、共働きの両親の代わりにご飯をつくるようになったことがきっかけでした。将来的にはパンづくりをしたいと思いながらも、大学卒業後は大阪のカノビアーノというイタリアンレストランに入り、料理の基礎を学ぶことにしました。カノビアーノは、植竹隆政さんという有名シェフがひらいた自然派イタリアンのお店で、ウッドベリーと同じように「素材の味を活かす」ことをコンセプトとしていました。イタリアンには珍しくバターや生クリームなどの動物性油脂や、ニンニク、唐辛子などを使用せず、さまざまな野菜や、その出汁、ハーブやスパイスなどを駆使して豊かな味わいを表現していました。振り返ってみれば、ヴィーガン料理をつくるための基礎は、カノビアーノで鍛えられたのでした。
そして私がコーヒー/カフェ文化に出会ったのは、カノビアーノを退職後、いくつかの飲食店で経験を積んだのち、ワーキングホリデー制度でオーストラリアのブリスベンに行ったときのことでした。オーストラリアは、家族で集まって朝食やブランチを食べるカフェ文化が盛んで、コーヒーのあまりの美味しさに衝撃を受けました。
オーストラリアのカフェ文化に影響を受け、帰国後は大阪のカフェレストランで働き、しばらく経ってからハワイにある別店舗のオーナーをすることになりました。私がヴィーガン料理を意識するようになったのは、そのころのことです。というのも、一緒に働いていたメンバーの三割程度がヴィーガンで、一緒にヴィーガンレストランに頻繁に行くようになったからです。2016 ~ 17 年ごろのことですが、その時点でハワイではカジュアルにヴィーガニズムを生活に取り入れる文化があり、その潮流は現在にまでつながっていると思います。
新型コロナウイルスの影響で日本にもどり、コーヒーと料理を両立できるお店を求めて、ウッドベリーに入社しました。当時はまだ渋谷店ができたばかりのころで、コーヒー屋としては知名度がありましたがフードはまだ充実していなかったため、メニューの開発を任され、自分が積み重ねてきたオーストラリアやハワイなどのカフェ文化の経験をすべて注ぎこみました。ヴィーガンメニューもふくめ、現在提供している料理・お菓子のベースは、そうした文脈のなかから生まれたものなのです。
日本での受容とトレンドの変化
ヴィーガンはしばしばベジタリアンと混同されることがありますが、ベジタリアンは菜食主義者の総称で、ヴィーガンもベジタリアンの一部です。ほかにも、ペスカタリアンやラクト・ベジタリアン、オボ・ベジタリアン、フレキシタリアンなど、なにを/どれくらいの頻度で食べるかによって、ベジタリアンにはさまざまなグラデーション/分類が存在します。
ヴィーガニズムは、より厳格な定義をつきつめるのであれば、食品に限らず身の回りのものもふくめて可能なかぎり動物性のものを使用しないような生き方ということになりますが、ベジタリアンがそうであるように、人によってグラデーションがあり、食品でも製造過程のどこまでを許容するのかという違いもあれば、ハワイのカジュアルなヴィーガンたちのように、その日の気分によって実践するような生活を送る人もいます。
日本でヴィーガンが注目を集めはじめたのは、五年ほど前からでしょうか。ちょうど私たちが提供を始めたのもそのころですが、東京でも十年前には数えるほどしかなかったヴィーガンレストランも、五年前あたりを境に有名なお店が出はじめ、いまではあちこちで新規開店しています。
先に述べたとおり、動物福祉や環境保護などのサステナビリティへの意識の拡大や、インバウンド需要の高まりがその要因として挙げられますが、そのほかにも健康・美容意識の増加と、それに付随してオシャレなライフスタイルとして捉えられている側面もあるでしょう。日本で新しくヴィーガン料理に興味をもった若い人たちのなかには、SNS やインフルエンサーの投稿に憧れたり、影響を受けたりした方もすくなくないはずです。カジュアルなヴィーガンと同様、ある種ファッション的に取り入れることへの賛否はあるとはいえ、それもまた世界的なトレンドの変化といえるでしょう。
また、それにともない、この数年で植物性食品(プラントベース)の流通が増え、大豆ミートなどの代替食品が一般的なスーパーにも並ぶようになりました。業者の取り扱いも変化し、日本でもヴィーガンフードがそれほど高くな値段で食べられるようになり、お店のレベルも年々上がってきています(しかしながら、代替肉のクオリティはまだ海外には追いついていません。海外のスーパーには大豆ミートのコーナーがあるほどにたくさんの商品が並び、競争が激しいぶん研究も盛んです)。
日本において、いまはまだ各料理ジャンルの著名なシェフがヴィーガン料理に本格的に参入するところまでには至っていませんが、そうなる未来も遠くないと思っています。今後、「ヴィーガンだから美味しい」という価値観が社会にひろまってゆくのはまちがいないでしょう。
ヴィーガン料理の魅力とその可能性
ヴィーガン料理は動物性食品を使用していないため、その美味しさは素材の味と密接にかかわり、素材の味をどれだけ活かせるかが肝になってきます。
日本は野菜がとても美味しく、ウッドベリーではこだわりのオーガニック野菜を使用していることもあって、シンプルに季節の野菜を鉄板で焼いて塩とオリーブオイルで食べたり、サラダをヴィーガン料理でよく使用されるフムス(ひよこ豆のペースト)とあわせて食べるだけでも、驚くほど美味しく、満足感を得ることができます。
お菓子・パンの場合も、通常のレシピのものと比べてクリーンな味わいになり、素材の味がより感じられるものになります。その点において、産地特性や繊細な味わいをもったスペシャルティコーヒーとの相性はピッタリです。ペアリングで楽しんだときに両方の香りをバランスよく感じていただけるのは、ヴィーガンレシピでつくったお菓子やパンならではの美味しさです。
国内外を問わず、私が経験したなかでとくに興味深く感じたのはオーストラリアのヴィーガンレストランでした。新しい料理だからこそ自由な発想でつくることのできるヴィーガン料理は、いわゆる「オーストラリア料理」と呼ばれるものがないようにさまざまな調理法をミックスしたジャンルレスな料理が数多く存在するオーストラリアの食文化と相性がよいのだろうと思います。
私自身も、和食やお寿司以外にも、イタリアンやパンづくりを学び、ハワイやオーストラリアなど、いろいろな国で料理をつくってきたため、ヴィーガン料理は自分の経験をミックスして活かすことのできる、自由で魅力的なジャンルの料理だと感じています。
ただ、ヴィーガンに注目が集まっているといっても、まだ偏見が残っていたり、その思想的な背景への理解が十分に行き届いているとはいえず、日本社会にヴィーガニズムやヴィーガン料理がひろく浸透するにはもうすこし時間がかかるかもしれません。
だからこそ、ウッドベリーではどんな人でも楽しめるヴィーガン料理を追求することで、まずは私たちが食をとおしてサステナビリティに貢献していきたいと思っています。そして同時に、その発信にも積極的に取り組んでいきたいと思っています。